事業内容
- DX推進/IoT開発事業
- AI/ROBOTICS開発事業

製造業や工場での業務効率化に課題を感じていませんか?毎日の受発注データ入力や在庫管理など、繰り返し作業に多くの時間を取られている現場は少なくありません。
RPAを導入すれば、定型作業を自動化し、作業時間の削減やヒューマンエラー防止が可能です。
本記事では、製造業でのRPA導入メリットや活用事例、成功のポイントまで詳しく解説します。
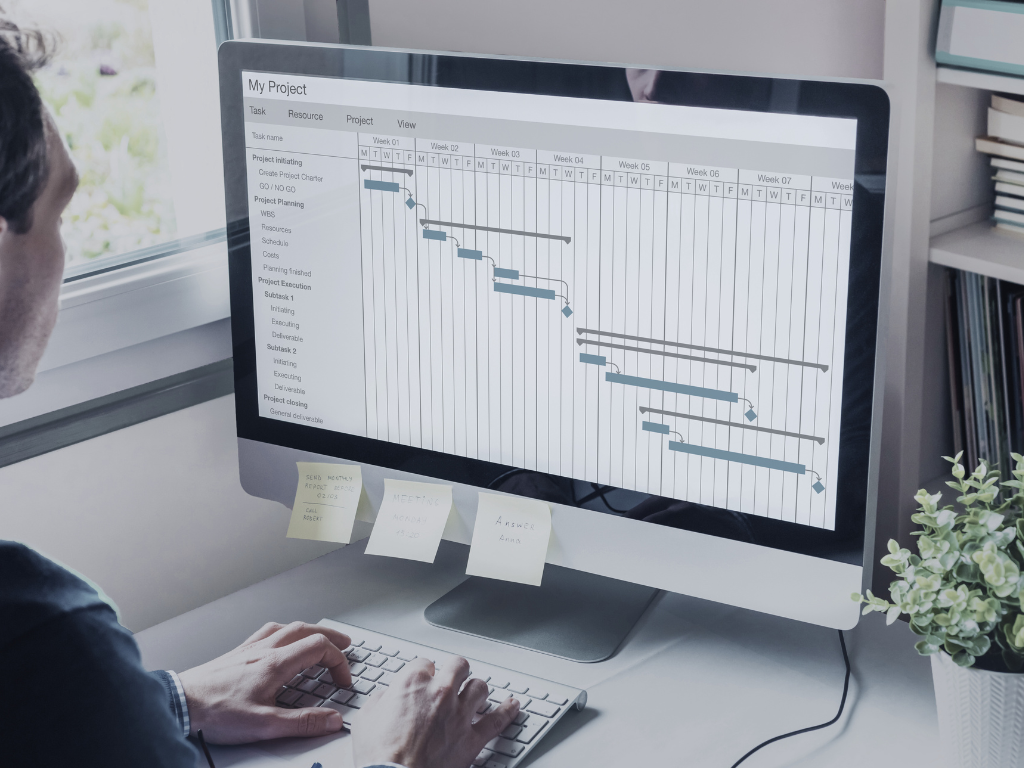
RPA(Robotic Process Automation)とは、コンピューター上で行う定型的・繰り返し作業を自動化するソフトウェアのことです。人が手作業で行っていたデータ入力、集計、帳票作成、システム間のデータ転記などを、ソフトウェアロボットが代わりに実行します。これにより、作業効率の向上やヒューマンエラーの削減が期待できます。
製造業の現場では、部品発注や在庫管理、Web-EDIデータの入力、作業実績の集計など、毎日繰り返される業務が多く存在します。こうした業務にRPAを導入することで、現場担当者の負担を軽減することが可能になります。

製造業においてRPAを導入すると、日々の定型作業や繰り返し業務を自動化でき、さまざまなメリットを得られます。5つのメリットについて解説します。
工場では受発注データの入力、在庫管理、作業報告の帳票作成など、日常的に同じ作業が繰り返されます。これらをRPAに任せることで、担当者はデータ入力や転記など単純作業にかけていた時間を削減できます。
結果として、品質改善のための分析や生産計画の検討など、より付加価値の高い業務に取り組めるようになり、工場全体の作業効率が向上し、生産性の大幅な向上につながります。
工場では数字の入力やデータ転記などでヒューマンエラーが発生しやすい作業があります。RPAを導入することで、こうした作業を正確に自動処理できるため、品質管理や受発注業務、経理作業の精度が向上します。工場内での情報精度が高まることで、生産計画や納期管理の信頼性も向上します。
RPAは作業手順を統一して自動化できるため、担当者ごとの作業のばらつきをなくし、属人化を防ぎます。新しい担当者でも同じ精度で業務を遂行できるため、教育や引き継ぎの負担も軽減されます。これにより、工場全体で安定した運用が可能になり、現場のトラブル対応もスムーズになります。
RPAによる作業時間の短縮は、残業代の削減や外注費の削減につながります。また、定型業務を自動化することで人手に依存していた運用コストを抑え、導入費用を上回る長期的なコスト削減効果が期待できます。生産ラインの効率化とあわせて、経営面での効果も大きくなります。
工場ではWeb-EDIや生産管理システム、基幹システムからのデータ収集や更新作業が日常的に発生します。RPAを導入することで、これらのデータ処理を自動化できるため、手作業による集計や転記の手間を削減できます。
リアルタイムで最新データを把握できることで、生産状況の監視や品質チェック、在庫調整などの意思決定が迅速になり、業務改善や生産効率向上につながります。

製造業の工場では、日々大量のデータ処理や繰り返し作業が発生します。これらの業務は定型的でありながら時間と手間がかかり、人手によるミスも起こりやすいという課題があります。そこでRPAを活用することで、パソコン上で行う作業の自動化が可能となり、作業効率や精度の向上、担当者の負担軽減につながります。
以下では、工場業務における代表的なRPA活用の例をカテゴリ別に紹介し、それぞれの効果を詳しく解説します。
工場では毎日、複数の取引先から発注データが送られてきます。RPAを導入していない場合は、担当者がデータを基幹システムに手入力する必要がありますが、RPAを導入することでWeb-EDIやメールで届いた発注情報を自動でシステムに登録できます。これにより、入力ミスの防止や作業時間の短縮が可能です。
さらに、RPAは受注状況をリアルタイムで更新できるため、在庫管理や生産スケジュール調整の精度も向上します。
部品や原材料の在庫管理は、正確さとスピードが求められます。RPAを導入していない場合は、棚卸表を作成し、複数のシステムやエクセルで在庫数を集計する必要があります。RPAは在庫システムから必要な情報を自動で取得・集計し、帳票を作成します。
その結果、工場全体の在庫状況を瞬時に把握でき、欠品や過剰在庫を防ぐとともに、現場スタッフの作業負担も軽減されます。
生産ラインでは、毎日の生産実績や品質チェック結果を記録する必要があります。これらのデータを手作業で入力すると、入力ミスや遅延が発生しやすくなります。RPAを使用することで、各システムから必要なデータを自動で取得し、基幹システムに登録できます。
また、異常値や不良品が発生した場合には、RPAがアラートを出す設定も可能です。これにより、早期に問題を発見でき、品質改善につなげられます。
工場では、作業実績や生産ラインの稼働状況をまとめた報告書を日々作成します。RPAは、必要なデータを複数のシステムから自動で抽出し、指定のフォーマットに整えて帳票を作成できます。
これにより、報告書作成にかかる時間を大幅に削減でき、データ分析や改善策の検討など、より重要な業務に注力できるようになります。
工場従業員の勤怠データを集計し、給与システムに入力する作業もRPAで効率化可能です。出勤状況や残業時間を自動集計し、給与計算に反映させることで、ヒューマンエラーを防ぎつつ、事務作業の時間を大幅に削減できます。
RPAは単なる入力作業の自動化だけでなく、データの抽出や集計を通じて分析作業を支援できます。例えば、生産ラインの稼働率や品質検査結果を自動で集計し、グラフやレポートに反映させることで、工場全体の状況をリアルタイムで把握できます。これにより、改善施策の検討や生産計画の最適化がスピーディーに行えます。

製造業の工場でRPAを導入する際には、単にツールを導入するだけでは十分な効果を得られません。業務内容や現場の実態に合わせた計画的な運用が不可欠です。
ここでは、RPA導入を成功させるために押さえておきたい6つのポイントを紹介します。各項目を実践することで、工場業務の効率化や作業ミスの削減、担当者の負担軽減など、RPAの効果を最大化できます。
工場でRPAを導入する際は、まず 自動化すべき業務を明確にすること が重要です。例えば受発注データの入力、部品や原材料の在庫管理、作業報告書の作成など、定型的で繰り返しが多い作業や、複数のシステムをまたいで行う作業は、自動化による効果が大きく、短期間で成果を実感しやすい業務です。
導入前に優先順位をつけることで、RPAによる効率化やコスト削減の効果を最大化できます。
RPAは、現場の作業手順や例外対応を正確に理解して初めて効果を発揮します。例えば、ライン作業の稼働実績や品質チェックデータの入力方法を現場担当者からヒアリングし、業務フローを図にまとめて可視化することで、どの手順を自動化するかが明確になります。これにより、導入後の入力ミスやフローの不具合を減らし、安定した運用が可能になります。
工場全体にいきなりRPAを導入するのではなく、まずは 一部の業務や部署で試験的に運用するパイロット導入 が推奨されます。
例えば、受発注処理や日報の自動作成など、影響範囲が比較的小さい業務で試すことで、業務フローの問題点やシステム上の改善ポイントを事前に洗い出せます。さらに、現場担当者がRPAの仕組みや操作感を理解できるため、本格導入時にスムーズに受け入れられます。
RPAは導入後も業務の変化に合わせて更新が必要です。例えば、生産ラインの工程変更や使用システムのアップデートに伴い、自動化フローの修正や例外処理の見直しを行います。定期的なレビューとメンテナンスを行うことで、RPAの安定稼働を確保し、導入効果を長期にわたって維持できます。
RPAを工場で定着させるには、 運用担当者や管理者の役割を明確化し、責任体制を整える ことが欠かせません。例えば、RPAの監視・保守担当者、エラー発生時の連絡ルート、改善策の報告ルールを設定することで、トラブル対応や効果測定がスムーズに行えます。
RPA導入の成果を定量的に可視化して社内で共有することも重要です。例えば、受発注入力の時間削減量、在庫管理でのミス削減件数、帳票作成にかかる作業時間の短縮などを数値で示すことで、現場や経営層の理解を得られます。成果を見える化することで、改善施策の検討や追加導入の判断も迅速に行え、工場全体でのRPA活用が進みやすくなります。

RPAを活用することで、単純作業を自動化し、業務効率や精度を大幅に向上させることが可能です。以下では、製造業におけるRPA導入の活用事例と、その効果についてご紹介します。
製造業の工場では、毎日複数の取引先から送られてくる受注データの処理が大きな負担となっていました。手作業でデータを基幹システムに入力していたため、入力ミスや作業時間の長さが課題となっていました。
そこで、RPAを導入することで、Web-EDIやメールで届いた受注情報を自動でシステムに登録できるようになりました。これにより、入力ミスを防止しつつ、作業時間を大幅に削減でき、部門担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に取り組む環境が整いました。
導入後1年で、月間約1,400時間の作業時間を創出という成果が得られました。特に複数システムから必要なデータを抽出し分析用グラフを作成する作業がRPAにより効率化されました。これにより、タイムリーな受注状況の把握と迅速な生産計画の見直しが可能になっています。
ある製造業の工場では、従来、仕掛品を含む在庫データや生産設備の稼働実績を手作業で管理しており、入力ミスやデータ更新の遅れが課題となっていました。
そこで、IoT端末を使って生産設備の稼働状況や作業数量、在庫数などをリアルタイムで取得し、RPAが夜間に生産管理システムへ自動連携する仕組みを導入しました。これにより、従来手作業で行っていた生産実績や在庫情報の入力が不要となり、入力ミスや遅延が解消されました。
さらに、仕掛品を含む在庫データの精度が向上し、これまで5日かかっていた棚卸作業も2日に短縮しました。リアルタイムでの進捗管理が可能になったことで、生産遅延や在庫不足を早期に検知し、迅速な対応ができるようになりました。
国内大手菓子メーカーでは、営業部門での販売動向把握を目的にRPAを導入しました。従来は60以上の得意先のPOSデータを週1回手作業で取得していましたが、RPAによりWebサイトから毎日自動でデータを収集できるようになりました。
この仕組みにより、得意先ごとの販売状況をほぼリアルタイムで把握できるようになり、営業活動の戦略立案や販売施策の検討も迅速に進められるようになりました。担当者は単純なデータ収集作業から分析や改善提案といった業務に取り組めるようになりました。
さらに、生産管理や経理部門でもRPAを活用し、基幹システムへのデータ登録や伝票作成の自動化を実現しています。
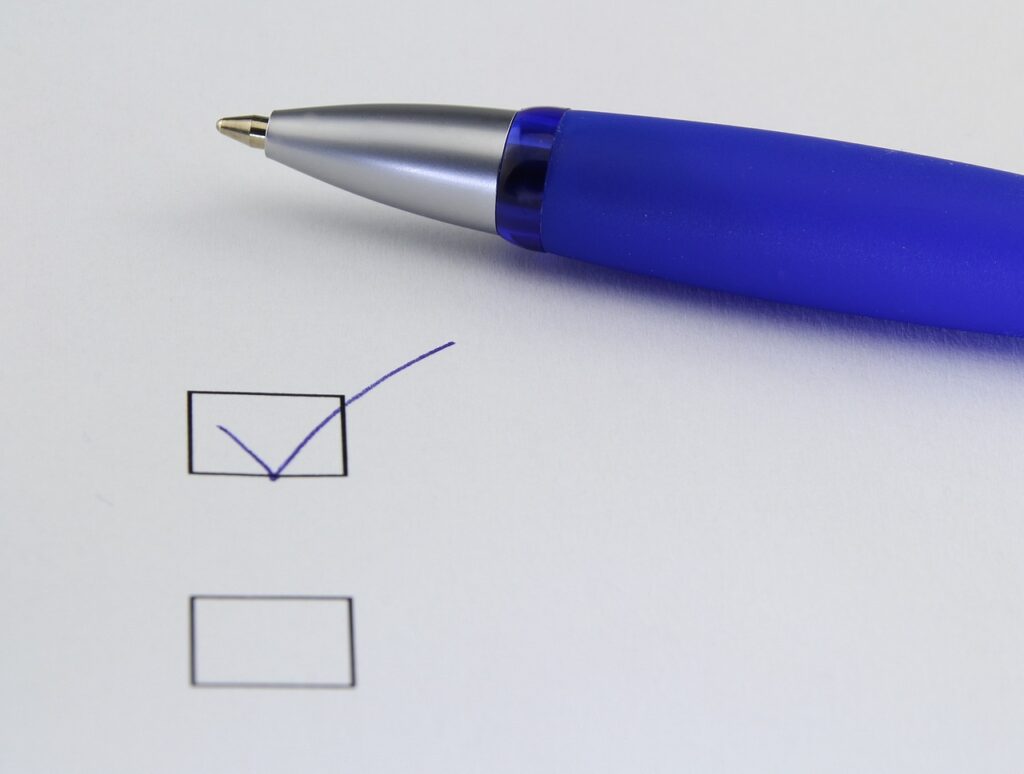
製造業の工場でRPAを導入する前には、事前にいくつかの重要なポイントを確認しておくことが重要です。単に自動化ツールを導入するだけでは、期待した効果を得られない場合があります。ここでは、工場でRPAを導入する際に確認すべき4つのポイントを紹介します。
RPAはすべての業務に適しているわけではありません。定型化されており、ルールが明確で繰り返し作業が多い業務を中心に選定することが重要です。具体的には、受発注データの入力、在庫管理や部品発注の処理、検査結果の記録などが該当します。
また、業務フローを可視化し、ボトルネックや手作業によるミスの多い箇所を把握することで、RPA導入の効果を最大化できます。
RPAはシステムやデータにアクセスするため、セキュリティや情報管理体制の整備が不可欠です。導入前に、アクセス権限の管理、データの暗号化、ログ管理の方法を確認し、情報漏えいリスクを低減する仕組みを構築しておく必要があります。また、社内規程や法令に基づいた運用ルールを策定し、関係者に周知することも重要です。
RPAは導入後の運用や保守が業務の継続的な効率化に直結します。障害発生時の対応手順や、定期的な業務フローの見直し、バージョンアップ対応など、運用・保守体制をあらかじめ確立しておくことが必要です。担当者の役割や責任範囲を明確にし、トラブル時に迅速に対応できる体制を整えておくと安心です。
RPA導入には初期費用や運用コストがかかるため、ROIや費用対効果を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
導入対象業務の作業時間削減効果、人件費削減効果、ミス削減による品質向上効果などを具体的に見積もることで、投資判断の精度が高まります。また、定量的な効果と合わせて定性的なメリットも整理することで、経営層への説明がしやすくなります。

RPAを導入する際、工場の現場担当者や管理者からはさまざまな疑問や不安の声が寄せられます。どの業務が自動化できるのか、IoTやAIとの違いは何か、導入を内製で行うべきか外注すべきかなど、事前に理解しておくことが導入成功のカギとなります。ここでは、工場でのRPA導入に関するよくある質問とその回答をご紹介します。
ルール化された定型作業を自動実行します。「手順が安定」「例外が少ない」「入出力がデジタル(CSV/Excel/画面)」といった条件がそろうと自動化に向いていると言えます。
受発注入力:Web-EDI/メール添付CSVの取り込み→基幹システム登録
在庫・棚卸:複数システムや表計算の照合→集計→帳票整形
品質データ登録:検査結果・不良率の日次アップロードとグラフ更新
帳票作成:日報・週報・月次レポートのフォーマット自動整形・配信
勤怠・給与:勤怠収集→人事/給与システム連携
設備点検記録:点検シート/センサーCSVの取り込み→履歴更新
都度判断が必要になる作業や過去のデータ・事例と照らし合わせる必要がある場合には、AI/OCRやルール整備とともに行うのが望ましいです。
役割が異なり、組み合わせで効果を最大化できます。
IoTで稼働データを収集 → AIで異常スコア算出 → RPAがMES/ERPへ結果を登録・アラート配信
RPA導入の進め方としては、まず外部の専門家に立ち上げを支援してもらい、その後の運用や改修は社内で内製化していくのが現実的です。
外部支援を活用する初期段階では、短期間での導入や設計品質の担保、そして過去の失敗事例に基づくリスク回避の知見を取り込めるため、立ち上がりの不確実性を大きく減らせます。
一方、運用フェーズに入れば、日々の小さな画面変更や例外対応に素早く手を打ちやすく、コストも最適化しやすい内製体制が強みを発揮します。社内にノウハウが蓄積され、継続的な改善のスピードも上がっていきます。
どこまで外部に頼るか、どのタイミングで内製へ移すかの判断は、対象業務の数や変更頻度、社内IT人員のスキルと人数、予算、そして求める投資回収スピードといった要素を踏まえて決めると良いでしょう。
製造業におけるRPAの導入は、作業時間の削減や人的ミスの低減、業務プロセスの標準化など、多くのメリットをもたらします。受発注や在庫管理、生産管理など、日常業務の幅広い領域で効率化が可能です。
導入の成功には、自動化対象の選定や現場との連携、効果の可視化が重要となります。実際にRPAを活用することで、データ収集や分析の精度向上、作業負荷の大幅軽減が実現できます。
ASTINAでは、IoT・AI・ロボティクス技術を活用した現場向けソリューションを提供しており、RPA導入の企画から運用まで一貫して支援可能です。導入に関するご相談は、ぜひASTINAまでお問い合わせください。