事業内容
- DX推進/IoT開発事業
- AI/ROBOTICS開発事業

現場の状況をリアルタイムで把握したい、作業効率や品質を向上させたい――そんな課題を抱える方に注目したいのがスマートセンシングです。
従来の計測では得られなかった判断や自動化を可能にする技術で、製造業・物流・農業などさまざまな現場で成果を上げています。
本記事では、仕組みやメリット、導入ステップと事例をわかりやすく解説します。

スマートセンシングとは、単に「データを計測する」だけの従来のセンシング技術と違い、センサーで取得したデータをAIやIoT技術と組み合わせて解析・活用し、現場の状況をリアルタイムで把握・判断する技術です。単なる「測定」から「判断・最適化」までを自動化できるのが特徴です。
従来のセンシング技術は、温度や湿度、圧力などの物理データを計測し記録することが主な役割でした。取得したデータは人が確認し、必要に応じて分析や判断を行うため、リアルタイムでの自動制御や最適化には限界がありました。
一方、スマートセンシングは従来のセンシングに加え、収集したデータをAIやIoTと連携して解析し、自動で判断や制御まで行える点が大きな特徴です。
たとえば、工場の生産ラインではセンサーが振動や温度を計測し、異常を検知するとAIが自動でラインを調整したり警告を発したりします。農業分野では、土壌の水分や日照量をリアルタイムで取得し、AIが解析することで灌漑の最適なタイミングを判断できます。
スマートセンシングは産業や農業の現場では作業効率の向上やリスク低減、品質改善など、従来にはなかった価値を生み出すことが可能になります。
| 従来のセンシング | スマートセンシング | |
|---|---|---|
| 主な機能 | データ取得(温度・湿度・圧力など) | データ取得+分析+意思決定支援 |
| データ活用 | 人手で確認・分析 | AIやクラウドで自動解析・最適化 |
| 活用例 | データログの記録 | 自動警告・生産ライン最適化・農作物の自動管理 |
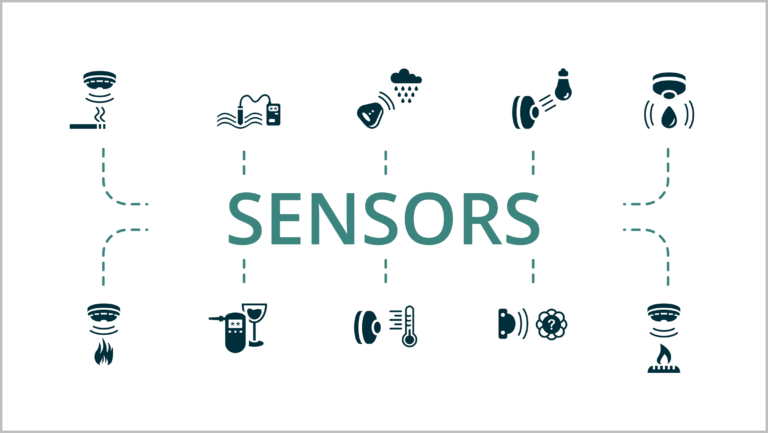
スマートセンシングは、IoTと組み合わせることで初めてその価値を発揮します。IoTとは、さまざまな「モノ」にセンサーや通信機能を搭載し、インターネットを通じてデータを送受信できる仕組みです。
スマートセンシングでは、この仕組みを活用してデータをリアルタイムで収集・解析し、現場の状況に応じて自動で判断や制御を行うことが可能になります。単体では測定だけに留まるデータも、IoTとAIを組み合わせることで現場の最適化や自動化に活かせます。
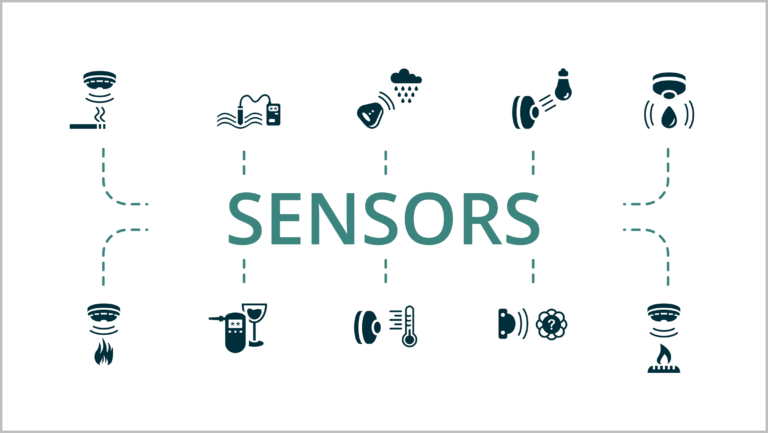
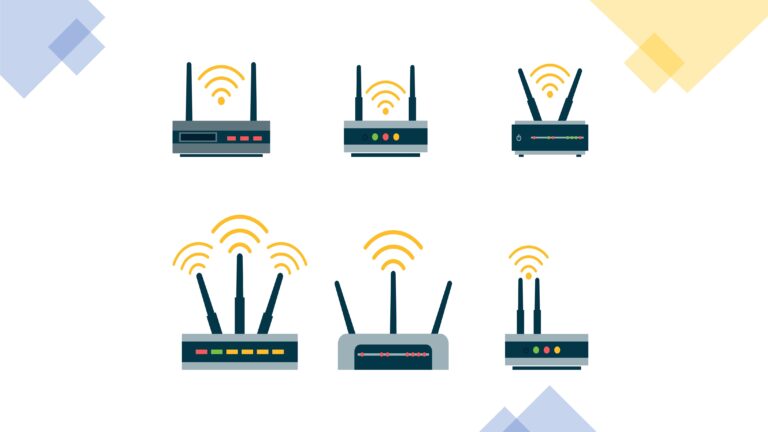
スマートセンシングでは、単一のデータだけでなく、複数種類のデータを組み合わせて収集することが可能です。これにより、単純な測定にとどまらず、AIやIoTを活用したリアルタイム解析や自動制御が実現できます。
産業現場や農業、物流、環境管理など、多様な分野で活用できる点がスマートセンシングの大きな特徴です。
| データの種類 | 具体例 | 主な活用用途 |
|---|---|---|
| 物理データ | 温度、湿度、圧力、振動、加速度 | 機械や設備の状態監視、環境管理 |
| 位置・動きのデータ | GPS情報、移動距離、モーター回転数 | 物流管理、機器稼働状況の把握、自動運転 |
| 画像・映像データ | カメラ映像、光学センサー | 品質検査、異常検知、施設監視 |
| 音・振動データ | 騒音、異常音、振動解析 | 設備異常検知、機械保全、予防保守 |
| 化学・環境データ | CO₂濃度、酸素濃度、pH値、化学物質濃度 | 農業、環境モニタリング、工場の安全管理 |

スマートセンシングを導入することで、単なる「計測」に留まらず、現場全体の効率化や品質向上、安全性向上など、さまざまな効果が得られます。従来のセンシング技術では得られなかった情報の活用や、リアルタイムでの判断・制御が可能になる点が大きな特徴です。以下に詳しく整理します。
スマートセンシングは、センサーで収集したデータをリアルタイムで解析できるため、従来は人手で行っていた計測や確認作業を自動化できます。これにより、現場担当者の負担が軽減され、作業時間の大幅短縮が可能です。また、センサーでの自動計測により、計測精度やデータの一貫性も向上します。
さらに、データはクラウドやネットワーク上で共有できるため、複数拠点や遠隔地の状況も把握可能になり、作業効率の改善が全体レベルで実現します。スマートセンシングは、単なる作業の自動化にとどまらず、現場全体の運用効率を向上させる基盤技術となります。
スマートセンシングでは、異常やトラブルを早期に検知し、自動的に通知や制御を行えるため、事故や設備故障のリスクを未然に防げます。これにより、作業者の安全確保だけでなく、機械や設備の寿命延長にもつながります。
従来のセンシングでは異常の兆候を見逃すこともありましたが、スマートセンシングでは連続監視とデータ解析により、微細な変化も捉えることができます。これにより、人的ミスに依存せずリスクを管理できる、安全・安心な運用環境が構築可能です。
スマートセンシングは、現場環境や工程を常に正確に把握できるため、製造や生産の品質を安定させることが可能です。データの蓄積により、過去の傾向や異常発生パターンの解析も行えるため、品質改善のための科学的な判断が可能になります。
また、単なる異常検知だけでなく、プロセス最適化にも活用でき、品質の均一化や向上に役立ちます。従来は経験や勘に頼っていた管理も、データに基づく科学的な管理体制に変わります。
スマートセンシングにより、無駄な作業や資源使用を削減できることに加え、設備故障や不良品による損失も抑えられます。異常や劣化を早期に検知することで、計画的な保守・点検が可能になり、緊急修理や生産ライン停止によるコストを大幅に削減できます。
また、データに基づく管理により、エネルギー消費や資源使用の最適化も可能で、長期的な運用コストの低減に寄与します。スマートセンシングは、単なる測定機能以上にコスト管理や効率化に直結する技術です。
収集したデータをAIやIoTと連携することで、現場全体の高度な最適化が可能です。まずデータを可視化することで現場の状況を把握し、生産スケジュールの調整や設備稼働の最適化、作業手順の改善など、単なる監視に留まらず、データに基づいた意思決定や自動制御に直結します。
さらに、過去データの蓄積と解析により予測分析やシミュレーションも可能となり、現場運用の精度向上や迅速な対応が実現します。スマートセンシングは、現場の状況を「可視化」し、最適化と自動化を同時に実現する技術として活用できます。

スマートセンシングを効果的に導入するためには、単にセンサーを設置するだけでなく、導入目的の明確化から運用体制の整備までを一貫して計画することが重要です。以下では、導入の基本ステップを4段階に分けて解説します。
まず最初に行うべきは、現場の課題を正確に把握することです。 「どの工程で人手や時間がかかっているか」「どんな不良やトラブルが発生しているか」「どのデータが不足しているか」といった現状を分析します。
この段階で、センシングの目的(例:異常検知、稼働監視、品質向上など)を明確化することがポイントです。課題と目的を明確にすることで、以降の技術選定やシステム構築の方向性が定まります。
課題が整理できたら、次に必要な技術を選定します。スマートセンシングでは、温湿度・振動・画像・音・位置情報など、さまざまなセンサーが利用できますが、全てを導入する必要はありません。「どの情報を取得すれば課題が解決できるのか」を基準に、最小限で最大効果を発揮する技術を選ぶことが重要です。
また、データ収集後の分析や可視化に用いるIoTプラットフォームやAIツールの互換性、既存システムとの連携性も確認しておくと、導入後のトラブルを防げます。
技術選定が済んだら、実際の導入計画を立てます。 センサーの設置場所、通信環境、データ収集の頻度、クラウドやローカルでのデータ処理方式などを設計し、段階的に導入を進めるのが理想です。
また、IoT化やAI導入を同時に検討することで、単なるデータ取得に留まらず、リアルタイム分析や自動制御といった「次の一歩」につなげることができます。この段階では、PoCを実施して小規模に効果を確認し、問題がなければ全体展開する流れが一般的です。
導入後に最も重要なのが、運用と保守の体制を整えることです。センサーや通信機器は長期使用によって測定精度が徐々にずれることがあるため、定期的に測定の正確さを確認・調整する「キャリブレーション」が必要です。これにより、常に正しいデータを取得し、誤った判断や制御を防ぐことができます。
また、データの異常や欠損を早期に検知できる仕組みを構築し、収集データを継続的に分析して改善を重ねることで、システムの精度や現場の生産性をさらに高められます。AIモデルを用いている場合は、定期的な再学習やアップデートを行い、環境や条件の変化に対応することが重要です。
さらに、現場担当者への教育やマニュアル整備を進めることで、運用が特定の人に依存せず、安定した稼働体制を維持できます。

スマートセンシングは、製造業・物流・農業など多様な産業現場で具体的な成果を生み始めています。従来は見逃されていた設備のわずかな異常や、環境変化による品質リスクを、センサーとAI解析がリアルタイムに検知し、迅速な対処を可能にします。
ここでは、スマートセンシングが実際にどのように活用され、効率化・省人化・品質向上に貢献しているのか、代表的な産業事例を紹介します。
自動車部品メーカーでは、生産ラインの稼働状況や設備の状態をスマートセンシングでリアルタイムに監視しています。各機械に設置した振動・温度・圧力センサーからIoT経由でデータをクラウドに送信し、AIが解析。異常を自動検知すると警告を発信し、必要に応じてラインを停止することで設備故障や不良品を防ぎます。
従来の巡回点検や記録作業も削減され、作業員は異常対応や工程改善などに取り組むことができるようになりました。導入により設備稼働率が向上し、不良品発生率も低下しました。リアルタイムでのデータ可視化は、複数拠点のライン管理にも活用され、生産効率と品質管理の両立に役立っています。
ある食品物流企業では、倉庫内の温度や湿度をスマートセンシングでリアルタイムに監視しています。各倉庫に設置したセンサーからIoT経由でデータをクラウドに送信し、管理者は遠隔で環境状況を可視化できます。設定した閾値を超えると、自動で空調や除湿機が制御され、最適な保管環境が維持されます。
従来は人手による巡回確認や記録作業が必要でしたが、導入後は自動監視により作業負担を削減できるようになりました。温度や湿度の変動による食品の品質低下や損失を防ぎ、効率的な倉庫運営が可能になりました。また、データは長期的に蓄積されるため、季節ごとの温湿度変動の分析や改善施策にも活用されています。
大規模農園では、作物の生育環境を最適化するためにスマートセンシングを導入しています。土壌の水分や栄養状態、気温や日照量などをセンサーでリアルタイムに測定し、IoTを通じてデータをクラウドに送信しています。AIが解析することで、灌漑や肥料の最適なタイミングを判断できます。
従来は目視や経験に頼っていた管理作業も、自動化や可視化によって効率化できるようになりました。必要な水や肥料を適切に供給することで、作物の品質や収量を向上させつつ、資源の無駄遣いも削減可能です。また、収集したデータは長期的に蓄積され、季節や気象条件に応じた栽培計画の改善にも活用されています。
さらに、広域の環境情報や作物の生育状況を把握する場合は、リモートセンシングを組み合わせることで、農園全体の最適化や長期的な栽培計画の精度向上に役立ちます。

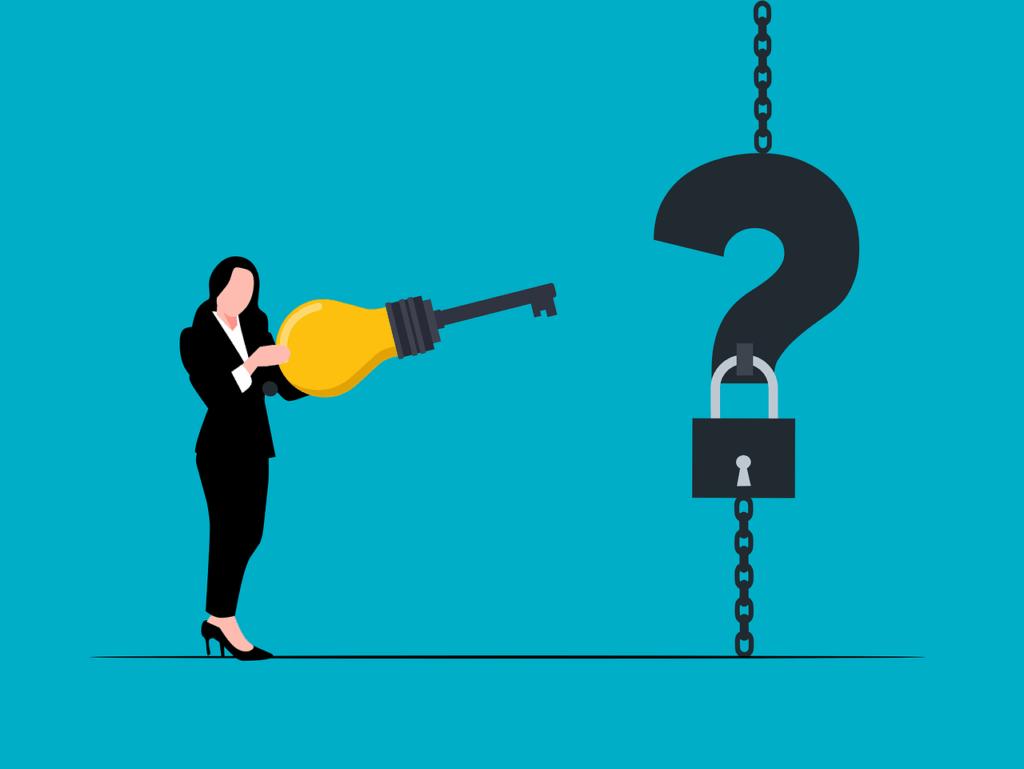
スマートセンシングは現場の効率化や品質向上に大きな効果をもたらしますが、導入時には技術面や運用面でいくつかの課題が発生しやすく、事前の対策が重要です。ここでは代表的な課題とその解決策を詳しく解説します。
スマートセンシングの効果は、センサーで収集するデータの正確さに大きく依存します。精度が低い、あるいは故障や通信不良によりデータが途切れると、異常検知や自動制御の判断が誤り、逆に生産や管理のリスクになることがあります。
用途や環境に応じた高精度のセンサーを選定することが重要です。また、センサーの定期的な校正やメンテナンスを計画的に実施することで、測定精度を安定させられます。さらに、複数センサーで同じデータを取得する冗長化や、異常値を自動補正する仕組みを組み込むことで、信頼性を高めることが可能です。
スマートセンシングでは多くのセンサーが連続的にデータを収集するため、日々大量の情報が蓄積されます。これを処理・解析する負荷が大きいと、リアルタイム監視や異常検知に支障をきたすことがあります。また、分析結果を活用した改善策の立案にも遅れが生じやすくなります。
クラウドやIoTプラットフォームを活用して、データの集約・保存・処理を効率化します。さらに、必要な情報だけを抽出するフィルタリングや、AIによる自動分析・異常検知を導入することで、分析負荷を軽減できます。これにより、現場担当者は重要な意思決定に集中でき、導入効果を最大化できます。
スマートセンシングやIoTの運用には、技術知識やデータ分析のスキルが必要です。社内に経験者が少ない場合、センサー設置や運用フローの整備が遅れ、導入効果が十分に得られないことがあります。
外部の専門コンサルティングやシステムベンダーを活用して導入を支援してもらう方法があります。また、段階的にセンサーやシステムを導入しながら担当者のスキルを習熟させることで、運用負荷を分散可能です。加えて、運用マニュアルや教育資料を整備することで、社内リソースの不足を補うことができます。
センサーの設置やデータ収集・解析、異常発生時の対応など、現場での運用フローが整備されていない場合、導入効果が限定的になります。データは取得できても、活用されずに埋もれてしまうこともあります。
導入前に、データ取得から解析、アラート通知、対応までの運用フローを事前に策定することが重要です。ルールを明確化し、担当者間で役割を分担することで、迅速な対応とデータ活用が可能になります。また、定期的なレビューと改善を行うことで、運用の精度や効率も向上します。
スマートセンシングは、センサーで取得したデータをIoTやAIで活用し、現場の判断や最適化まで実現できる技術です。
製造業・物流・農業をはじめ、多くの産業で省人化や品質向上、設備の安定稼働に貢献し、DX推進に欠かせない基盤となっています。導入成功のポイントは、現場の課題に応じたセンサー選定と、データを継続的に活用できる体制を構築することです。
ASTINAでは、AI外観検査装置「OKIKAE検査ボックス」をはじめ、現場に最適なセンサー活用を支援するIoT/AIソリューションを自社開発し、企画から実装、運用保守まで一貫して対応しています。スマートセンシングの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。