事業内容
- DX推進/IoT開発事業
- AI/ROBOTICS開発事業
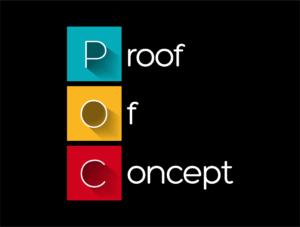
「PoCをやってみたのに、その後が進まない…」そんな経験はありませんか?
技術的に成功しているのに止まってしまう状態は「poc死」と呼ばれます。背景には意思決定プロセスの欠如や目的の不明確さがあります。
本記事では、poc死の本質と主要な原因、さらに成果を次フェーズにつなげる方法を詳しく紹介します。
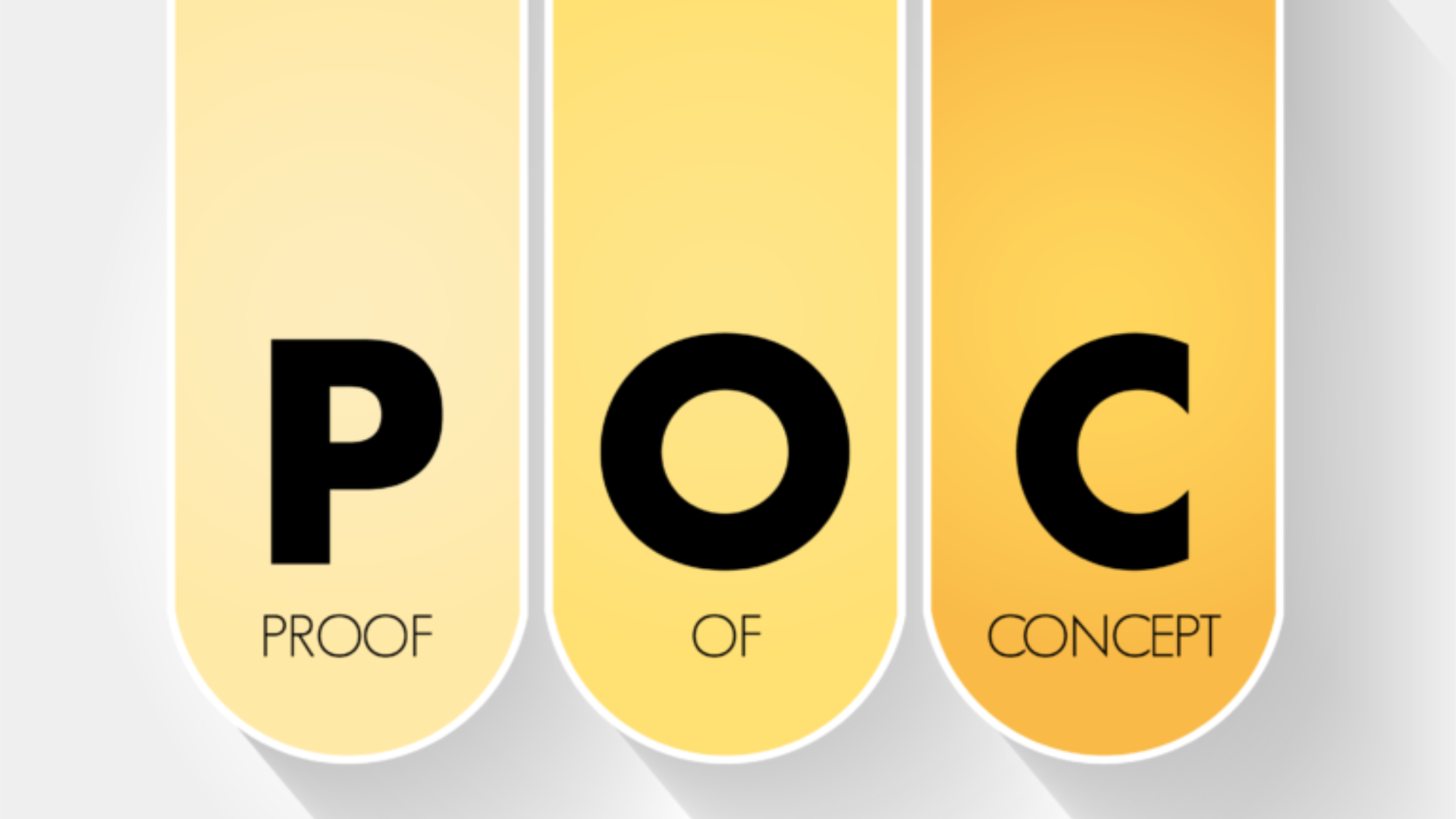

「PoC死」とは、PoCを実施したにもかかわらず、その成果が実運用や本格導入に繋がらず、プロジェクトが途中で頓挫してしまう状態を指します。
新しい技術やサービスの導入を検討する際に、まず小規模なPoCを行って実現可能性を検証しますが、製品化・本格運用などの次のステップへと移行できずに終わってしまうケースが少なくありません。このような状態を「PoC死」と呼びます。
PoCの失敗とPoC死は似ているようで、実はまったく異なる性質を持っています。
実証実験の目的が果たせなかったことを指します。たとえば、技術的に実現できなかった、想定していた精度やパフォーマンスが得られなかった、ユーザーのニーズに合わなかった、などが該当します。
これは、「この方法では課題が解決できない」という明確な結果が出たことを意味し、ある意味では前向きな失敗とも言えます。目的を明確にし、検証の枠組みが適切であれば、PoCの失敗も重要な学びや判断材料になるからです。
一方で、PoC死は「PoCは成功したのに、その先に進めない」状態です。
PoCの成果が出ているにもかかわらず、本格導入や開発に至らない理由はさまざまです。成功基準が曖昧、関係者の合意形成が不十分、意思決定プロセスが設計されていない、予算や体制が用意されていない、など「技術ではなく、組織・プロセス上の課題」が原因となることが多いです。
PoCを何度も繰り返すうちに、関係者や組織全体が疲弊し、モチベーションやリソースが枯渇してしまう状態を指します。
たとえば、複数の部門で同時並行的にPoCを進めた結果、現場の担当者が通常業務と両立できなくなったり、経営層が「またPoCか」と投資判断に慎重になったりするケースです。PoC自体が目的化してしまい、本来の課題解決や導入フェーズにつながらないまま「PoC疲れ」に陥ることがあります。
つまり、PoC疲れ=過剰な取り組みの積み重ねによる消耗、PoC死=個別プロジェクトが停滞して頓挫する状態と整理できます。両者は異なる課題ですが、いずれも企業のイノベーション推進を妨げる要因となるため、早期の対策が必要です。

本来の目的を果たせずに失敗に終わってしまう「PoC死」は、決して珍しい現象ではありません。PoC死が起こる原因について詳しく見ていきましょう。
PoCのスタート地点において、最も重要なのは「このPoCで何を達成したいのか」というゴール設定です。しかし明確な目標を持たずにスタートし、「技術を試してみる」という漠然とした理由だけで動き出してしまうプロジェクトもあります。この状態では、成果が出たとしても、それを「成功」と認める基準が曖昧なために評価が困難になります。
例えば、AIを使った異常検知のPoCで「80%の精度が出た」としても、その数字が現場の許容範囲なのか、ビジネス的に価値があるのかが不明瞭であれば、結局判断保留になり、次の段階へ進めなくなってしまいます。
このように、目的がはっきりしていないとPoCはただの“実験”に留まり、本導入のための意思決定材料として機能しません。したがって、PoC開始前に、技術的・業務的・ビジネス的に「成功の定義」を明確にすることが重要です。
PoCは単なる検証作業ではなく、その結果をもとに「導入するか否か」を組織として意思決定するためのプロセスです。しかし、PoCの段階で成果が得られても、誰がどのタイミングで何を判断するのかが事前に決まっていないと、その後のアクションにつながらず、プロジェクトが停滞してしまいます。
こうした意思決定フローの欠如は、PoCの成果を活かせない致命的な要因です。そのため、PoC開始時には、結果を評価し、次フェーズへ移行するための意思決定プロセスを設計し、必要な情報収集や報告体制もあらかじめ整えておくことが不可欠です。
PoCには多様な関係者が関わります。技術面を担当するIT部門、実際に使う業務部門、最終的な資金や方向性を決める経営層、そして外部のベンダーやパートナーなどです。しかし、それぞれの関心や優先順位が異なると、目的や評価基準にズレが生じやすくなります。
例えば、IT部門は「技術的に問題なく動いた」ことに満足しても、業務部門は「使い勝手が悪い」「業務フローに合わない」と評価が低いことがあります。また経営層はROIを重視するため、定量的な効果が見えなければ予算を承認しません。
こうした関心や評価の食い違いは、プロジェクトの推進にブレーキをかけ、結果としてPoCの成果が活用されない原因になります。このため、関係者間で目的や期待値、成功基準を共有し、共通の理解を持つことが成功の鍵となります。
PoCは小規模かつ限定的に行われるため、本番環境とは異なる条件で実施されることが多いです。しかし、本導入を念頭に置かずにPoCを設計すると、実際に運用しようとした際に様々な問題が発生します。
たとえば、PoCでは少量のデータで検証したが、本番では膨大なデータを処理しなければならず、システムが耐えられない。あるいは、PoC環境では特別に準備された人材が操作していたが、本番では一般の担当者が使うため操作性に問題が出る、などです。
本番との環境差が原因で「PoCではうまくいったが、本導入はできない」という結果を招きやすく、PoC死の一因となります。したがって、PoC設計時から本番環境での運用を意識し、可能な限り実環境に近い条件で実施し、運用体制やユーザー教育も視野に入れる必要があります。
PoCの成功には、検証作業だけでなく、データの収集・分析、関係者間の調整や進捗報告など、さまざまなタスクが伴います。しかし、現場によってはPoCが「通常業務の合間に行う追加作業」とみなされることがあり、担当者のリソースが十分に確保されないケースもあります。
さらに、PoCを自社内だけで完結させようとし、専門的な支援を受けずに進めることも、失敗の一因となりがちです。特に、過去にPoCの経験が少ない企業では、検証設計・評価方法・リスク管理などにおいて見落としが生じやすく、プロジェクトが思うように進まなくなるケースがよく見られます。
必要に応じて、PoC支援に実績のある外部パートナーに相談することで、社内の負担を軽減し、成果を確実に次のフェーズへつなげる体制を構築しやすくなります。

PoCで得られた成果を次のステップへと繋げるためには、PoCの設計そのものが成功の鍵を握ります。PoC死を防ぐには、ただの実験としてではなく、「事業の意思決定に直結するプロセス」として設計する必要があります。
以下で、PoC死を防ぐための基本設計のポイントを解説します。
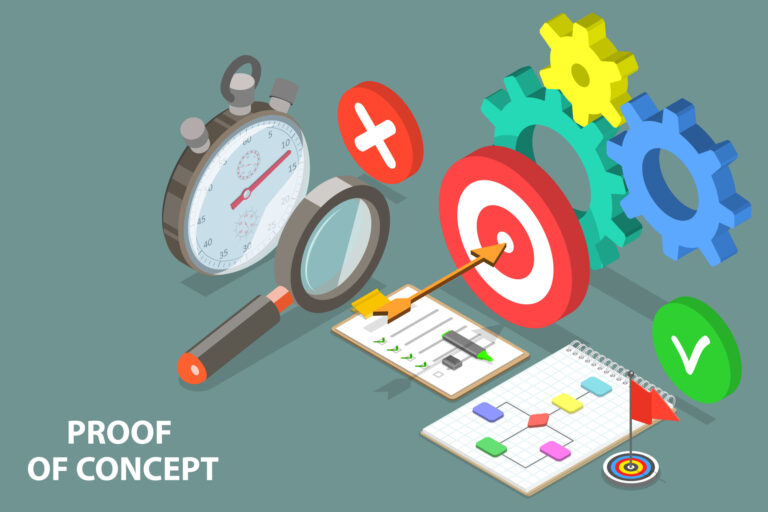
まず最初に、「このPoCで何を検証したいのか」を明確にすることです。目的が曖昧なままPoCを進めると、結果をどう判断するべきかが分からなくなり、関係者の中で評価がバラバラになりがちです。その結果、誰も意思決定できず、PoC死に繋がります。目的を最初に定義し、関係者全員で共有することがスタートラインです。
「何をもって成功とするのか」をあらかじめ明確に定めておく必要があります。ここで重要なのが、定量的な指標(数値目標)と定性的な評価基準(質的な成果や現場の納得感)の両面から成功条件を設定することです。
定量的な指標の例としては、「検出精度90%以上」「処理時間が従来比で50%短縮」「誤検出率5%未満」といった具体的な数値を用います。こうした数値は後の評価段階で客観的な判断材料となり、導入可否や次フェーズへの移行をスムーズに進める材料になります。
一方で、定性的な基準はたとえば「現場担当者が運用可能と感じるか」「技術的な障壁の有無を把握できたか」など、現場の肌感覚や業務適合性といった側面もPoCの成否を分ける重要な判断材料です。
これら両方の指標を明確にし、関係者と共有しておくことで、曖昧な判断を避けることができます。
PoCでは「すべてを試す」ことは不可能です。 「全機能を検証しようとしてPoCの規模が膨れ上がる」「業務全体に適用しようとする」など、過剰な設計をすると時間もリソースも足りなくなり、結局どれも中途半端な結果になります。
そのため、PoCはスモールスタートが原則。 「最も重要な業務フロー」や「代表的なユースケース」に絞り、必要最小限の範囲で実施することが設計上の重要ポイントです。
PoCは理想環境ではなく、「実運用に近い条件で」設計することが重要です。 検証時に使うデータの量や質、関わる人のスキルレベル、システム連携の有無など、本番を想定したリアルな制約を前提にPoCを設計します。現実感のない設計は、PoC成功 → 本導入失敗 というパターンに直結します。
PoCが終了した後に「次のステップへ進めるかどうか」を、誰がどの基準で判断するのかをあらかじめ決めておくことが重要です。よくある失敗例として、結果を報告しても誰も判断せずに放置されたり、稟議が提出されても承認が先送りにされてしまったり、といった“宙ぶらりん状態”が挙げられます。
PoCはビジネス価値を見極め、本導入への道筋をつけるための重要なプロセスです。にもかかわらず、自社のリソースやノウハウだけで完結しようとすると、どうしても視野が限られ、失敗のリスクが高まってしまいます。
そのため、PoCの初期段階から信頼できる外部パートナーと連携することが効果的です。技術とビジネスの両方に強みを持つパートナーを巻き込むことで、課題の整理、成功条件の設定、導入を見据えた設計をスムーズに進めることができます。
「まずは自分たちだけで試してみよう」と考えがちですが、それがPoC死につながるケースも少なくありません。PoCを単なる実験で終わらせず戦略的に成功へ導くためには、信頼できる外部パートナーと協働体制を構築することが欠かせません。


前述したとおり、PoCで成果が得られても、本番導入や開発フェーズに進めないまま止まってしまうケースは少なくありません。これが「PoC死」と呼ばれる状況です。
PoCを成功させるだけでは不十分であり、PoCの成功とは「次に進める状態」にすることにほかなりません。その成果をどのように次のフェーズにつなげるかが、プロジェクトの命運を分ける重要な分岐点となります。PoCの“次”に確実に進むために、以下のような視点と準備が不可欠です。
PoCで良い結果が出ても、「技術的に実現できた」だけでは経営層や投資判断部門を動かせません。
成果をビジネス観点から再構成し、数値データに加えて利用者の反応や業務変化といった定性的効果、さらに導入後の費用対効果を示す必要があります。あわせて、導入による業務や体制への影響、システム面の変更やリスクも整理し、全体像を示す提案に仕立てることが求められます。
PoCで成果を出しても、開発資金の確保や人員不足、社内承認の停滞によって前に進めなくなることがあります。
これを防ぐには、PoCの段階から「次を見据えた設計」が欠かせません。本導入に必要な予算や体制を概算し、関係部署と調整を進めておくとともに、社内の申請フローを把握して準備を整えることが重要です。
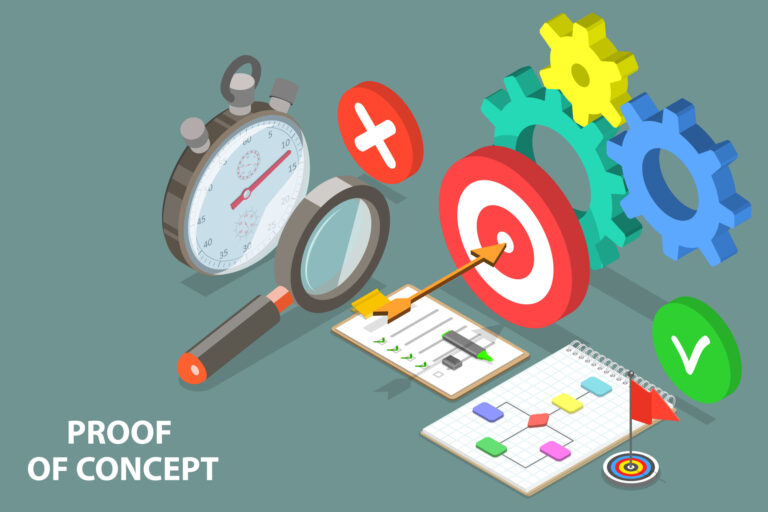
失敗事例をもとに、どのような点に注意すると改善につながるのかを見ていきましょう。以下に、事例を紹介します。
AIを活用した不良品検知のPoCを実施し、技術的には高い精度で成果を出しました。しかし、ビジネス部門と技術部門の連携が不十分だったため、「なぜこのPoCを行うのか」「導入によってどんな価値が生まれるのか」といった意義が経営層に伝わらず、本導入には至りませんでした。
技術的成果だけでなく、ビジネス上の意義や効果を関係者間で共有し、PoCの目的を全社的に理解させる仕組みが必要です。
あるIT企業は、先進的な技術を持つスタートアップとPoCを進めました。検証自体は問題なく進んだものの、評価指標が曖昧で、成果を社内に適切に伝えられませんでした。その結果、経営層から「導入効果がよく分からない」と判断され、プロジェクトは中断されてしまいました。
PoC開始時点で成功条件を定量・定性の両面から設定し、誰が見ても納得できる評価指標を用意することが重要です。
PoC環境での検証はうまくいったものの、実際の現場に導入しようとすると大量データ処理に耐えられず、システムが稼働しませんでした。原因は、PoC設計段階で「実運用条件」を十分に考慮していなかったことにあります。
PoCを特別環境で行うのではなく、データ量や利用者スキル、運用フローなど本番に近い条件を前提に設計することが欠かせません。
PoCは、単なる技術検証に留まらず、導入や事業展開につなげるための重要なプロセスです。しかし、目的の不明確さや関係者間の認識のズレ、本番環境を考慮しない設計などが原因で、多くのプロジェクトがPoC段階で止まってしまう「PoC死」に陥るケースがあります。
PoC死を避けるためには、まず原因を理解し、計画や設計の段階で適切な準備を行うことが重要です。特に、目的の明確化や成功条件の設定、現場や本番環境を意識した設計、関係者間の連携は、PoCの成果を次のフェーズにつなげるための基本となります。
ASTINAでは、IoT・AI・ロボティクスを活用した現場向けソリューションの提供を通じ、PoCの設計支援から導入まで一貫してサポートしています。PoCでの課題や次のステップで悩んでいる場合は、ぜひお問い合わせください。