事業内容
- DX推進/IoT開発事業
- AI/ROBOTICS開発事業

リモートセンシングの導入を検討しているものの、コストや解析方法に不安を抱えていませんか?
本技術を活用すれば、衛星やドローンを使った遠隔観測で、従来は困難だった広範囲の情報収集が可能になります。AI解析と組み合わせることで、予測や異常検知も実現でき、農業・防災・インフラ管理など幅広く活用できます。
本記事ではその仕組みと事例、課題解決策をわかりやすく紹介します。

リモートセンシングとは、人が直接現場に行かなくても、離れた場所から対象物や環境の情報を取得・観測する技術です。衛星、航空機、ドローン、地上設置型センサーなどを利用して、地形や作物、建物、気象状況などを非接触で測定できます。
従来の観測では、人手での計測や目視による確認が中心でしたが、リモートセンシングを活用すると広範囲かつ短時間でデータを取得できることが大きな特徴です。また、取得したデータは画像や数値データとして保存・解析できるため、AIやデータ解析技術と組み合わせることで、変化の予測や異常検知、業務効率化にも応用できます。
要点:観測の位置とカバー範囲が違います。
通常のセンシングは、工場設備や現場など特定の地点でセンサーを設置し、直接データを取得する方法です。
一方、リモートセンシングは離れた場所から電磁波を用いて対象を観測する技術であり、衛星や航空機、ドローンなどを利用して広範囲のデータを一度に取得できるのが大きな特徴です。
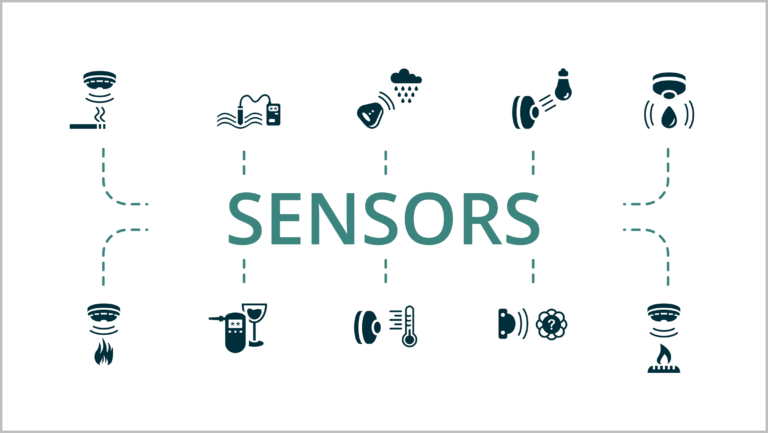
要点:スマートセンシングは「賢く使う仕組み」、リモートセンシングは「どこから観測するか」。
スマートセンシングは、センサー自体にデータ処理や通信機能、AI解析などの知能的要素を組み込むことで、取得データをリアルタイムに解析・活用できる仕組みです。
一方でリモートセンシングは、「どこから観測するか」に焦点を当てた概念であり、遠隔から広域の情報を取得することに特化しています。
リモートセンシングは広域データを取得する技術でありながら、AIやクラウド解析と組み合わせることで、スマートセンシング的なリアルタイム解析や業務プロセスへの直接活用も可能になります。このため、農業・建設・環境管理・製造業などでは、両技術を組み合わせることで効率化や精度向上が進んでいます。


リモートセンシングは、地表や対象物の状態を遠隔から高精度に把握・分析できる技術です。衛星やドローン、地上センサーなどを活用することで、人の目では捉えきれない広範囲の情報や時間的変化を効率的に取得できます。
以下では、リモートセンシングによって実現できる主要な機能とその特徴を詳しく見ていきます。
リモートセンシングを利用すると、広範囲の領域を短時間で一括観測できることが最大の特徴です。衛星やドローン、航空機などのプラットフォームを通じて、数十平方キロメートルから数百平方キロメートル規模の地形、施設、作物の状態などを一度に取得できます。
従来の現地調査では、人的リソースや時間の制約から不可能だった大規模観測が可能になり、データ収集のスピードと効率が飛躍的に向上します。また、取得したデータはデジタル化されるため、後の解析や可視化にすぐに活用でき、業務全体のフローを大きく改善できます。
リモートセンシングは、定期的な観測データの取得を通じて、対象物や環境の変化を時系列で把握することができます。地形や植生の変化、設備や構造物の劣化状況、気象条件の変動など、時間の経過に伴うパターンを可視化できるため、異常や傾向を早期に検出できます。
この機能により、予測・計画立案が可能になり、リスクを未然に防ぐことができるのが大きな利点です。さらに、データを連続して蓄積することで、季節変動や長期的な環境変化の分析など、高度なモデリングやシミュレーションにも応用できます。
リモートセンシングは、現場に赴かずに遠隔地の状況を常時監視できる点が大きな強みです。IoTセンサーやドローンと連携することで、観測対象の温湿度、振動、位置情報などを自動的に取得し、リアルタイムでデータを送信・解析できます。
この仕組みにより、人的な巡回作業や目視確認の手間を大幅に削減し、安全性や作業効率を向上させることができます。また、遠隔監視は災害時や危険区域でも有効で、人的リスクを回避しながら必要な情報を継続的に取得できます。

リモートセンシングは、AIや画像解析技術と組み合わせることで、異常やリスクの自動検知に活用できます。取得したデータから通常状態との差異を分析することで、目視では見逃しやすい微細な変化や損傷を特定可能です。
これにより、異常の早期発見や予防的対応が可能になり、メンテナンスや運用の効率化、リスク低減に直結します。さらに、異常検知の自動化はデータの精度向上にも寄与し、人的判断に依存しない一貫した監視体制を構築できます。

リモートセンシングは、対象物や現象から発せられる光や電磁波をセンサーで検知し、データ化して解析する技術です。ここでは、どのようなプラットフォームで観測するのか、そしてどのようなセンサーを使うのかを解説します。
リモートセンシングで情報を取得する際の観測の土台を「プラットフォーム」と呼びます。プラットフォームは、センサーを搭載して対象物や現象を観測する「乗り物・設置場所」のようなもので、観測範囲や解像度、機動性などに応じて使い分けられます。
適切なプラットフォームを選ぶことが、効率的かつ精度の高いデータ取得に繋がります。
地球の上空を周回しながら観測を行う衛星プラットフォームは、広範囲のデータを定期的に取得できる点が大きな特徴です。高度や軌道によって解像度や観測周期が異なり、数百キロメートル規模の広域観測から、数メートル単位の詳細観測まで対応可能です。
気象観測、森林・農地の広域モニタリング、災害被害の迅速把握など
航空機プラットフォームは、衛星より低高度を飛行するため、高解像度で柔軟な観測が可能です。飛行経路や観測エリアを自由に設定でき、特定地域に重点を置いた詳細なデータ収集が行えます。
都市部や工業地帯の変化観測、森林資源の管理、土壌や水域の詳細解析
小型・軽量で低空を自在に飛行できるドローンプラットフォームは、局所的かつ高精度な観測に適しています。地形や建物の影響を受けやすい場所でも柔軟に対応可能で、必要な場所や角度からデータを取得できます。
農地の作物状態チェック、建設現場の進捗管理、災害時の現地状況確認
地上プラットフォームは、観測対象の近くに設置する固定型または移動型のセンサーを指します。高頻度で連続観測が可能なため、微小な変化やリアルタイムでの監視に適しています。
構造物の振動監視、施設内環境モニタリング、設備や機械の状態観測
| 種類 | 代表例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 人工衛星 | LANDSAT、ひまわり | 広範囲・定期観測に適する |
| 航空機 | ヘリコプター、セスナ機 | 中規模エリアの高解像度観測 |
| ドローン | 小型UAV | 現場単位の詳細観測 |
| 地上観測装置 | 固定カメラ、LiDAR | 局所的・高精度データ取得 |
リモートセンシングで取得されるデータは、観測対象や目的に応じてさまざまな種類のセンサーによって収集されます。各センサーは利用する波長や検知原理が異なるため、捉えられる情報の特性や解析方法も異なります。
ここでは、リモートセンシングで代表的に用いられるセンサーの種類と、それぞれがどのような情報を取得できるのか、その特徴と活用例について詳しく見ていきます。
光学センサーは、可視光(人間の目で見える範囲)や近赤外線の波長を用いて、対象物の画像や映像を取得するセンサーです。可視光と近赤外線を同時に観測できるものもあり、植生や土地の状態の違いを定量的に評価することが可能です。
光学センサーの利点は、色や形状、パターンなどを視覚的に確認できる点にあります。ただし、雲や霧、夜間など光の条件に影響されやすいため、天候や時間帯に応じた運用が必要です。
気象観測、森林や農地の広域モニタリング、災害被害の迅速把握、土地利用や都市環境の分析
赤外線センサーは、対象物が放出する熱エネルギーを検知し、温度分布を画像化するセンサーです。昼夜や暗所を問わず観測が可能で、温度異常や熱源の位置を特定するのに適しています。ただし、雲や雨、湿度の影響を受けやすいため、観測条件の管理が重要です。建物や設備の熱管理など、温度変化を定量的に把握したい場合に有効です。
建物や設備の温度監視、河川や湖沼の水温把握、火災や熱源の位置特定、災害時の安全確認

マイクロ波やレーダーを用いたセンサーは、対象物に電磁波を照射して反射や散乱の情報を取得します。光学センサーとは異なり、雲や雨、昼夜の影響を受けにくく、全天候での観測が可能です。また、地形や構造物の変化を精密に検知できるため、災害やインフラ管理の分野で有効です。
地滑りや洪水など災害の監視、氷河や河川の変化観測、橋梁・道路の沈下や構造変化の確認

マルチスペクトルやハイパースペクトルセンサーは、可視光、赤外線、近赤外線など複数の波長帯を同時に観測できるセンサーです。単一の画像では見えない情報を取得できるため、植生の健康状態、水質、土壌の特徴などを詳細に解析できます。精密な環境評価や農作物管理に特に有効です。
作物や森林の健康状態評価、水域や土壌の環境調査、災害前後の環境変化の把握
LiDARセンサーは、レーザー光を対象に照射し、その反射までの時間を計測して距離を算出します。これにより、地形や構造物の正確な3Dモデルを作成可能です。高精度な立体情報を取得できるため、地形解析や建設現場、森林管理に幅広く活用されます。
地形や都市の3Dマッピング、森林や樹木の立体解析、土砂災害や洪水リスクの評価

| センサー | 取得するデータ | 主な用途 |
|---|---|---|
| 可視光センサー | 目に見える光 | 地図作成、都市監視 |
| 赤外線センサー | 熱放射 | 温度分布、植生状況 |
| マイクロ波センサー | 反射強度、反射時間 | 雨量測定、地表変化解析 |
| LiDAR | 距離データ | 3D地形モデル、構造物測定 |

リモートセンシングは、遠隔から対象の状態を観測・解析できる技術で、環境保全、農業管理、防災、インフラ、交通など幅広い分野で活用されています。ここでは主要な活用分野と具体例を紹介します。
リモートセンシングは、地球規模から地域規模まで、広範囲の自然環境や災害リスクを効率的に把握できる技術です。従来は現地調査やサンプリングが必要だった森林の状況や河川の水位、地滑りや火山活動なども、衛星や航空機から取得したデータで迅速に確認できます。
また、気象衛星からの情報を組み合わせることで、天気予報や災害予測の精度向上にも貢献します。このように、リモートセンシングを活用すれば、人的リソースを大幅に削減しつつ、安全かつ継続的に環境や災害の監視が可能になります。
農業分野では、リモートセンシングを活用することで、作物の生育状況や土壌の状態を遠隔で把握でき、従来の目視や現地巡回に頼る方法よりも効率的な管理が可能になります。衛星やドローンによって得られる画像やセンサー情報を解析することで、適切な施肥や灌漑のタイミングを判断できるほか、病害虫の早期検知や収穫時期の最適化も支援できます。
これにより、生産効率や収量の向上だけでなく、品質管理やコスト削減にもつながるため、スマート農業の重要な基盤技術となっています。


建設・インフラ管理分野では、リモートセンシングを活用することで、従来の測量や現場確認では困難だった広域の地形や構造物の状態を正確に把握できます。LiDARや高解像度カメラにより、道路や橋梁、ダムなどの3Dモデルを作成し、設計や施工計画の精度を向上させることが可能です。
また、構造物の劣化や変形を定期的にモニタリングすることで、安全性の確保や保守計画の最適化にも役立ちます。このように、リモートセンシングは、建設現場や都市インフラの効率的かつ安全な管理に不可欠な技術です。
海洋や沿岸域の観測でも、リモートセンシングは重要な役割を果たしています。海水温や海流、赤潮の発生状況など、広範囲かつ継続的なデータを取得することができるため、漁業や海洋環境保護、災害予測に活用されています。また、サンゴ礁や海洋生態系の調査、沿岸浸食や水質の変化の把握にも有効です。
従来は現地での潜水調査やサンプル採取が中心でしたが、リモートセンシングを使えば短時間で広域のデータを取得できるため、効率的かつ安全に海洋環境の状況を理解することができます。
自動車や交通管理においても、リモートセンシングは広域の道路状況や交通流、インフラの状態を把握する手段として活用されます。車両搭載型センサーとは異なり、遠隔から観測可能な衛星やドローン、固定カメラネットワークを用いることで、都市全体や高速道路などの広域の交通情報をリアルタイムで取得・解析できます。

リモートセンシングは広範囲かつ高精度な情報取得を可能にする技術ですが、導入にあたってはいくつかの課題があります。ここでは主要な課題と、その解決策を紹介します。
リモートセンシングを導入するには、衛星画像の取得費用やドローン・センサーの購入・運用費、解析ソフトウェアやデータ管理システムの導入など、初期投資や運用コストがかかります。また、取得したデータの量が膨大になるため、解析には専門知識や高度な処理能力も必要です。
このため、中小規模の企業や現場では導入をためらうケースがあります。さらに、通信環境やデータ容量の制約によって、クラウドへのデータ送信や解析が難しい場合もあります。
クラウドサービスや外部データプロバイダーを活用することで、初期設備投資を抑えつつスケーラブルに運用できます。また、AIによる自動解析ツールを組み合わせることで、膨大なデータ処理や人的コストを削減可能です。
これにより、中小企業でも効率的にリモートセンシングを活用し、現場の監視・予測・管理に役立てることができます。
リモートセンシングでは大量のデータを取得できますが、それを正確に解析・活用するための専門知識を持つ人材が不足しています。解析能力が十分でない場合、取得したデータを業務改善や意思決定に活かしきれず、投資効果が低下する恐れがあります。
AIによる自動解析やクラウドベースの分析プラットフォームを活用することで、専門知識がなくてもデータを効率的に活用できます。また、データ連携基盤を整備すれば、異なる部署やシステム間で情報を統合・共有でき、解析作業の効率化や意思決定の迅速化にもつながります。
衛星やドローンを使った観測は、天候や季節、日射条件などの影響を受けやすく、取得データに誤差が生じる場合があります。特に、雲・雨・霧などがある場合には、画像の解像度や精度が低下することがあります。
複数の観測手段(衛星+ドローン+地上センサーなど)を組み合わせるマルチモーダルデータ収集や、AIによるデータ補正・ノイズ除去技術を活用することで、観測精度を高めつつ安定した情報取得が可能です。また、クラウド上でリアルタイムにデータを統合・解析することで、環境変動の影響を最小化できます。
リモートセンシングは、遠隔から広範囲のデータを取得・解析し、時系列の変化監視や異常検知、リスク管理を可能にする先進技術です。衛星、航空機、ドローン、地上プラットフォームなど、多様な手段で環境・農業・建設・交通など幅広い分野に応用できます。一方、導入コストやデータ解析の専門人材不足、天候による誤差などの課題も存在します。
ASTINAでは、IoT・AI技術を活用したハード・ソフト一体型のソリューションで、リモートセンシングの活用を現場に最適化することを目指しています。企画から開発・導入支援・運用まで一貫対応し、現場のデジタル化・効率化をサポートします。リモートセンシング導入やIoT活用のご相談は、ぜひASTINAまでお問い合わせください。